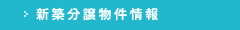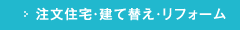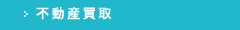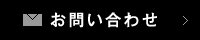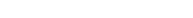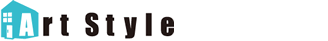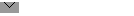親族間売買と一般的な不動産売買の違いとは?
親族間で不動産を売買するときに、思わぬ税金が発生したり、トラブルが発生したりする可能性があります。
親族間売買における知識を身につけ、トラブルを回避しましょう。
今回は、親族間売買と一般的な不動産売買の違いについてお伝えします。
不動産を親族間売買するときの注意点も解説するので、ぜひ参考にしてください。

□親族間売買と一般的な不動産売買の違いとは?
親族間売買が一般的な不動産売買と違う点は4つです。
1.仲介手数料がゼロ
親族間売買の場合に多くの人は不動産売買ではなく、個人間売買をします。
個人間売買であれば、不動産会社に払う仲介手数料を支払う必要がありません。
2.みなし贈与だと判断される可能性
親族間で不動産を売買するときに、不動産の価格を通常よりも低くして売る方が多くいます。
不動産の時価と売却価格に差がありすぎると、その差額がみなし贈与だと判断されるかもしれません。
みなし贈与だと判断されると、贈与税が課せられるので、時価と売却価格が離れすぎないように気を付けましょう。
3.税金の控除や特例が使えない
買主が売主の配偶者であったり、直系血族であったりする場合は、税金の控除や特例が使えません。
4.住宅ローンの審査が通りづらい
金融機関は住宅ローンの不正利用を警戒するため、親族間売買の場合、ローンの審査が通りづらいです。
特に築年数が古い実家を売買するときはローンの審査が通りづらいので、注意しましょう。
□不動産を親族間で売買するときの注意点をご紹介!
*適正な価格で売買する
不動産を時価よりも格安で売買するとみなし贈与と判断され贈与税が課せられる可能性があります。
売る相手が親族であったとしても、適正な価格で売買しましょう。
*売買契約書を作成する
親族間売買であっても、売買契約書は作りましょう。
売買契約書は不動産を売買したことの証拠にもなるので、作成するのをおすすめします。
売買の証拠がないと贈与とみなされてしまうかもしれません。
*相続人の同意を得る
不動産を相続人の1人に売却する場合は、相続人となる親族全員に売却することの許可を取りましょう。
そうしないと、後々相続のトラブルが発生する可能性があります。
□まとめ
親族間売買は、仲介手数料がかからなかったり、売買価格が時価と違いすぎるとみなし贈与と判断されたり、税金の控除が使えなかったり、住宅ローンの審査が通りづらかったりする点で一般的な不動産売買とは違います。
親族間で不動産売買するときは、みなし贈与だと判断されないように適正な価格で売買をしましょう。
また、売買契約書をつくることも大切です。
堺市にお住まいの方で不動産の売却についてご不明点がある方は、お気軽に当社にご相談ください。